ピアノの調律というと、「専門家の仕事で、自分には関係ない」と思う方も多いかもしれません。
でも、実はその作業の中には、誰にとっても共感できる“心を落ち着かせる要素”が隠れているのです。
音階やユニゾンを丁寧に合わせていくとき、調律師は深い集中力を発揮します。
その感覚は、雑念を払って一文字ずつ写経を書くような、静かな瞑想体験にも似ているのです。
この記事では、私が体験している「ピアノ調律の魅力」や「ゾーンに入る感覚」について、ちょっとお話させて頂きますね。
1. 音階・ユニゾンとは?ピアノ調律の基本
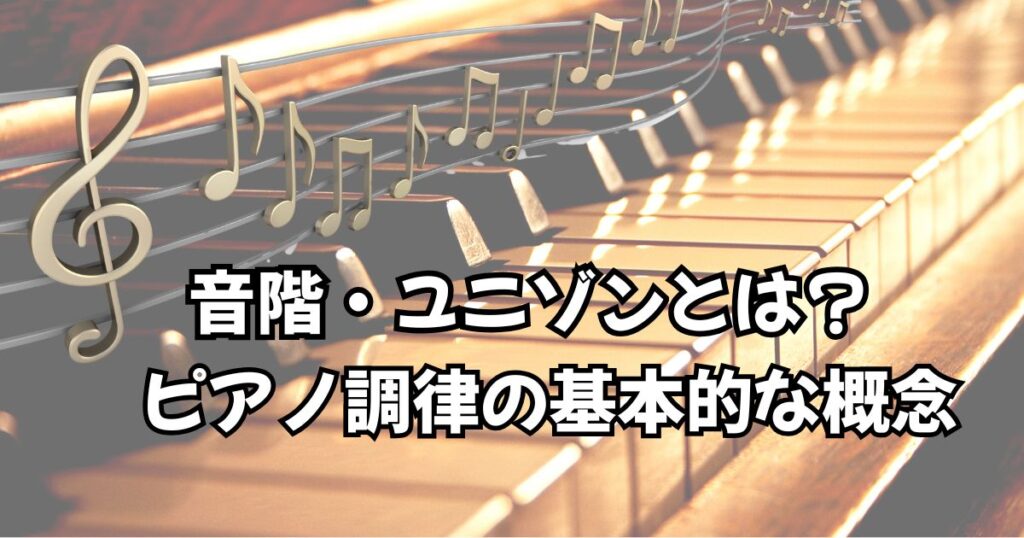
ピアノの中には約230本の弦が張られています。例えば、1つの音(例えば「ド」)は一本の弦だけでなく、多くの場合2〜3本の弦が同じ高さの音を出すために張られています。
この複数の弦を「ユニゾン」と呼びます。
ピアノ調律師の大切な仕事は、一つひとつの音が正確な音階で鳴るようにし、そしてそのユニゾンの弦同士の音がピタリと合うように細かく調整すること。
たとえわずかなズレでも、ユニゾンが合っていないと、耳障りなうなりや不快な響きを感じてしまいます。
2. 調律における集中の重要性と瞑想的要素
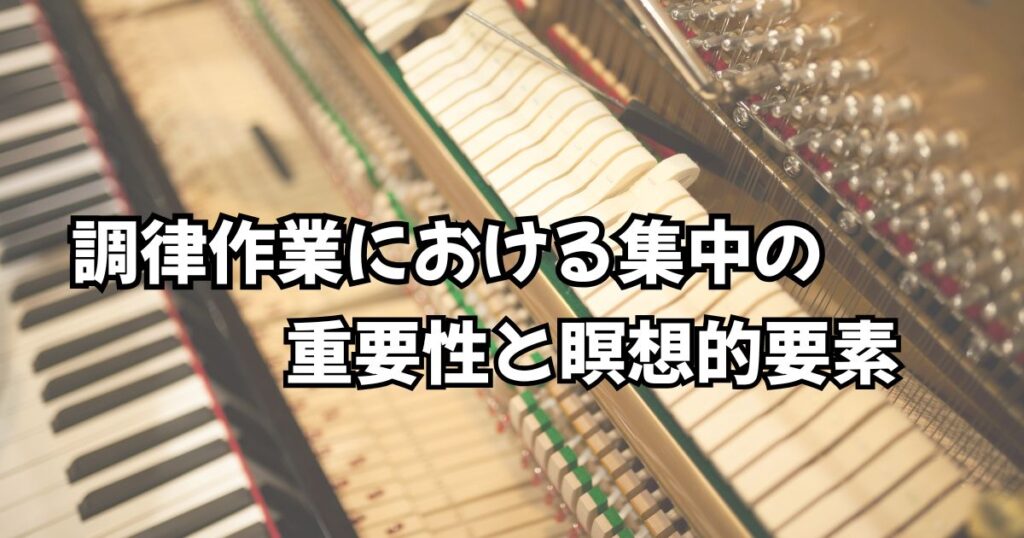
調律の作業は単純に弦を締めたり緩めたりするだけではなく、聴き分ける力が必要です。
微細な音の差を常に探りながら、手先の感覚も研ぎ澄まされていきます。
この作業中は、周りの音影響は最小限で、自分の内側に向き合うような集中状態に入ります。
こんな繰り返しの調整は、ただ機械的に行うのではなく、自分とピアノとの対話とも言えます。
気持ちを静かにして無心に向き合うと、まるで瞑想をしているような精神状態になるのです。
このような状態になると、たとえ周りで園児がワイワイ遊び回っている保育園でも、きちんとピアノの音だけが頭の中で鳴っているんですよね。
3. 写経に似ている?調律の繊細さとリズム感
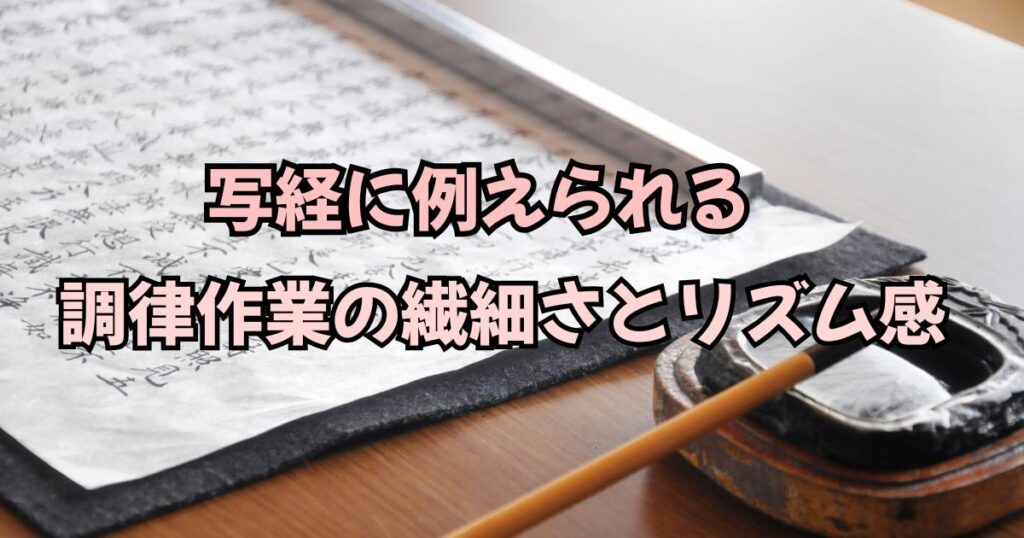
写経とは、文字を一字ずつ丁寧に書き写すことで、集中力と心の平穏を養う仏教の伝統的な修行の一つですよね。
ピアノ調律もとても繊細な作業で、小さな音の微調整を繰り返します。
調律師の手は、一つの音を完璧に調えるために、リズミカルに細かく動きます。写経の筆運びのように、一筆一筆を大切に進めるその姿勢には、共通する精神性が感じられます。
お客様からも「調律の音を聴いているだけでも気持ちよくなりますね」とか「前の調律師よりリズムがとても良かったけど、上手下手に関係あるの?」と言われることが度々あります。
実際にリズムが技術の上手下手に関係あるかは分かりませんが、リズムを刻むと速くて疲れない調律が出来るのは確かです。
4. 調律中に体験する「ゾーン突入」感覚とは
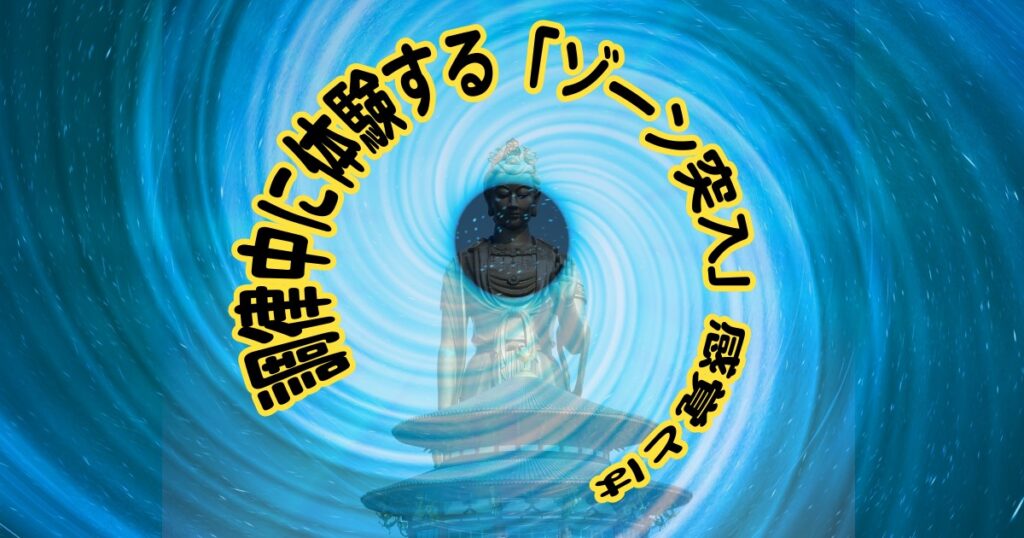
調律(音合わせ)を続けていると、「時間を忘れる」「周りのことが気にならなくなる」と言われる「ゾーン」に入る瞬間があります。
この状態になると、感覚が研ぎ澄まされ、心も体も軽く、まるで音に溶け込んだかのような感覚で、次々と音を正確に合わせられます。
この「ゾーン」はアスリートや芸術家が最高のパフォーマンスを出すときにも現れるもので、私にとっても、この時間こそが調律の醍醐味であり、やりがいでもあります。
日常や子育ての悩みからも開放されて、本当にスッキリした気分になれるんですよ。
でも、毎回「ゾーン」に入れるわけではないので、もっともっと技術的にも精神的にも精進が必要なんでしょうね。
5. 調律を通じて得られる心の安定と自己成長
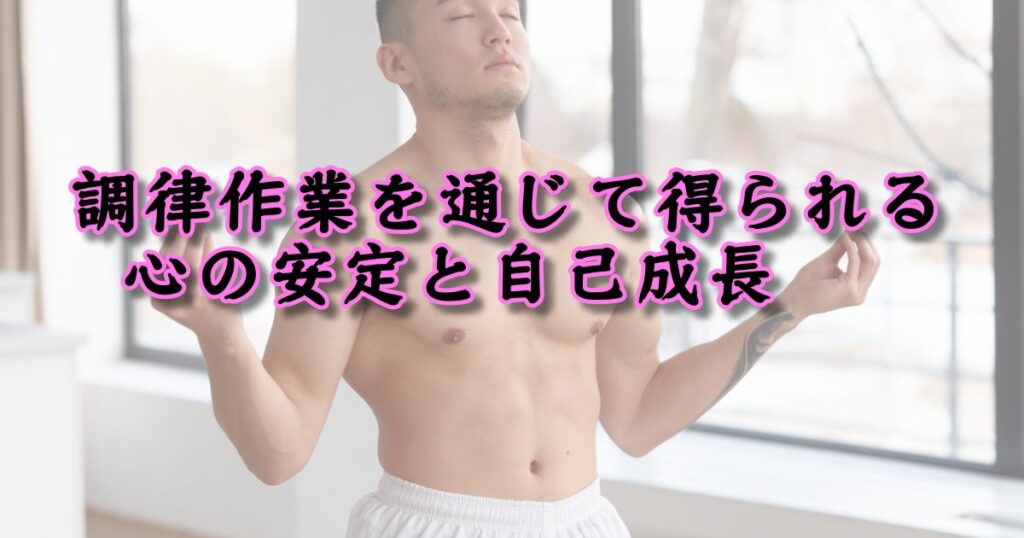
日々の調律作業は、単なる音の調整だけでなく、自分自身の心を整える時間にもなります。
小さな変化に気づき、いくつもの音を調和させる中で、自然と忍耐力や集中力、そして自分をコントロールする力が磨かれていくのです。
また、「心が落ち着く」「自分の居場所を見つけた感じがする」などの感覚は、多くの調律師が経験しており、調律という仕事がただの技術ではなく、精神的な自己成長の場でもあることを私は実感できて、調律師っていい仕事だな~って思う瞬間です。
余談ですが、当社の税務を10年担当してくれた税理士さんが、退職されるまで「調律師」を「ちょうきょうし」って言い間違えてた事を思い出しました!(笑)
けっこう、お馬さんの「調教師」に間違えられるのは調律師アルアルなんですよね…。
6. まとめ
ピアノ調律は、単に「音を合わせる技術」だけではありません。
音階やユニゾンを丁寧に調整する繊細な作業は、写経のように集中力を高め、心を落ち着かせる瞑想的な体験を得られます。
調律の過程で訪れる「ゾーン」に入る感覚は、深い集中と充実感をもたらし、私にとって何物にも代えがたい瞬間。
そして、調律を通じて得られる心の静けさや自己成長は、この仕事の大きな魅力なのです。
もし、ピアノ調律に少しでも興味があるなら、ぜひこの繊細で深みのある世界に触れてみてください。
その静かな魅力に、きっと魅了されるはずです。
私と父は、浜松にある「カワイピアノテクニカルセンター(現在のカワイ音楽学園)」で調律を学びました。
下記にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひご覧になって下さいね。

旧 カワイピアノテクニカルセンター(現在のカワイ音楽学園)
カワイ楽器が設立した調律師養成学校です。
ご興味のある方は御覧ください。


コメント